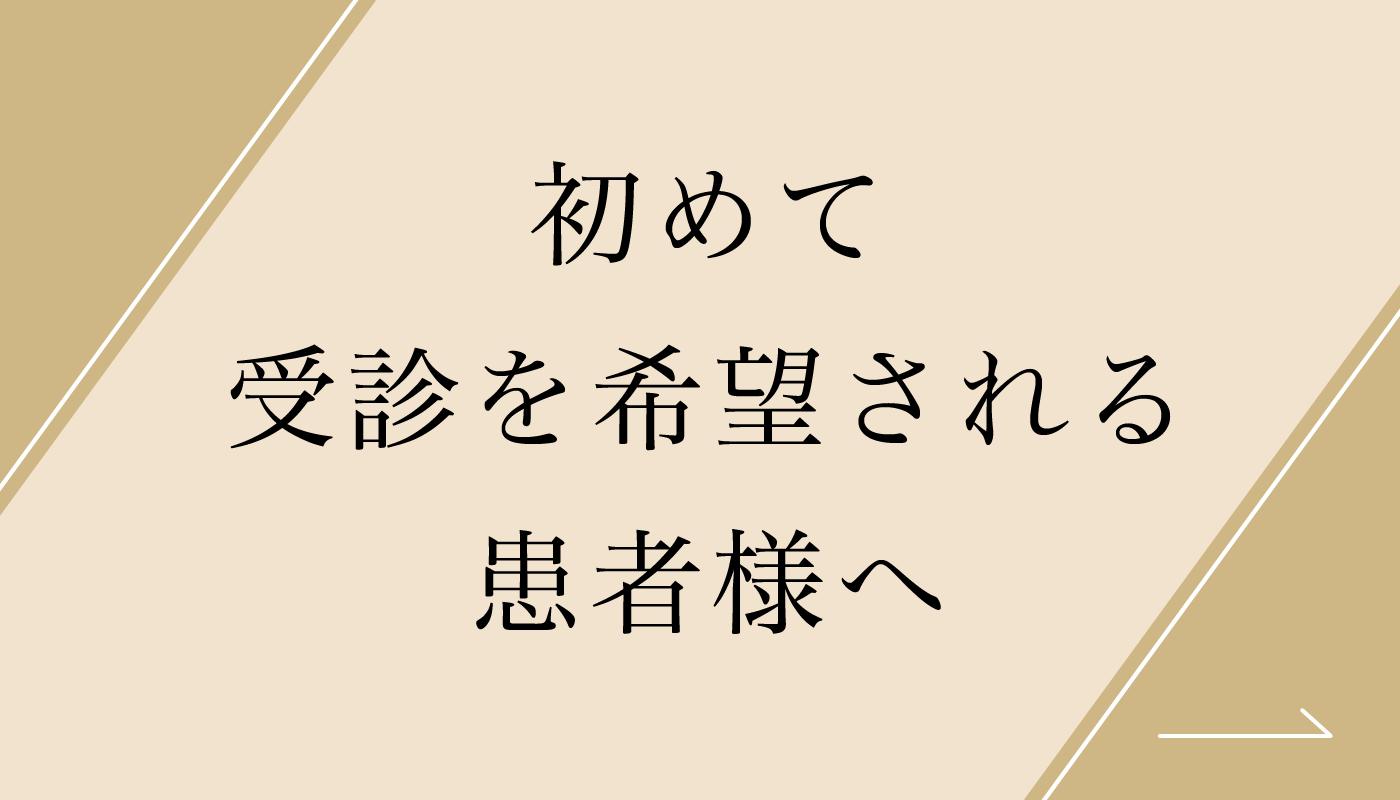アゴのコリ(咬筋)
||| ページ内目次
アゴのコリ(咬筋)解消としての
ボツリヌス療法の歴史

ボトックス®などのニューロトキシンを使用した咀嚼筋に対する治療は学術的に、1994年Smythらが咬筋肥大症7例の患者に対してBTX治療を行い、見た目の改善と食いしばりの改善に有効であったと報告しています。すでに30年以上の歴史のある治療方法です。
顔の中の最大の咀嚼筋、咬筋のあごのコリはくいしばり、歯ぎしりを併発することが多く、顎のだるさや痛み、顔が凝るなどのつらい症状です。
アゴのコリ(咬筋)の概要

カンファークリニックでは、アゴのコリ症状に対して、ボツリヌストキシン(BTX)治療をおこなっています。また、クレンチング症状、ブラキシズム症例、食いしばり、歯ぎしりの治療、詰め物やかぶせものなどの歯科補綴物が取れたり、外れたり、割れたりしないようにするための破折予防、インプラント手術直後のインプラントフィクスチャーに対する暫間的な過重予防手段としてもボツリヌストキシン(BTX)治療を応用しています。
顎コリとしての歯ぎしりやくいしばりの症状は、寝ているときやパソコンに向かっている間など、無意識のうちに繰り返されることが多く、咀嚼筋の中でも閉口筋である咬筋、側頭筋、内側翼突筋への繰り返される筋肉の負担が関与しています。歯ぎしりやくいしばり症状は、毎日の生活の中で頻繁に繰り返されるような常習性がなければ、それほど心配をすることはありません。
特別な治療をしなくても数日様子を見ることで改善します。しかし、寝ている間の歯ぎしりや、くいしばり、ブラキシズムやクレンチングは、無意識の中で、何度も繰り返され、その結果、歯や歯槽骨、顎骨周囲筋や頸部、肩甲骨、上腕周囲筋にも影響して、あごや肩や背中の筋肉が凝ります。そして、健康障害、睡眠障害を引き起こします。とくに顎コリは深刻です。顔面咀嚼筋が凝ってしまうと顎の痛み、顎のだるさと、ハリ感、しもぶくれ、むくみなど健康の障害が生じる部位です。
歯ぎしりやくいしばり、クレンチングやブラキシズムは、あごのコリに直結してあごの位置や噛み合わせ、咬合関係、顎関節症状、筋肉の電位などに影響します。噛みしめたことによって起こった顎コリ、歯ぎしりによって起こった顎コリ、食いしばりによって起こった顎コリを、院長が触診をして診断し治療をおこなっています。
アゴのコリ(咬筋)を
適応する患者様

口腔習癖(TCH)と呼ばれる無意識的なあごの運動の代表は、食いしばりや歯ぎしり、ブラキシズムやクレンチングです。顎コリ症状に対してボツリヌストキシンを使用した症状の緩和療法は、軽症~重症まで、多くの患者様に適応することが出来ます。
歯ぎしりや食いしばり、ブラキシズムやクレンチングの診断は重要です。
咬筋や側頭筋の肥大、こり、スパスム、筋膜のコリを診断してBTXを適応しています。また、インプラント治療をおこなっている患者様、インプラント治療後の即時加重症例に対する咬合圧の軽減治療にも応用しています。
しかし、精神的、心理的な要因が加わったこれらの症状に対しては、ボツリヌストキシン治療が第一選択ではなく、症状に応じた診療領域(整形外科、心療内科、眼科、形成外科)のドクターと連携、対診をおこなっています。
アゴのコリ(咬筋)の
治療計画と治療効果
顎コリに対しておこなうBTX-A治療は、顎コリ症状としてのくいしばり、歯ぎしり、ブラキシズムやクレンチングの改善、MPD(myofacial pain dysfunction)症状によっておこる、あごのだるさや痛み、ハリやむくみ、しもぶくれの緩和です。
食いしばりや歯ぎしりなどの口腔習癖の緩和または、顎コリによる筋肉疲労などの機能的、神経的な改善をおこないます。
| 副作用 | 一時的な副作用、副反応、併発症として、注入部位、注射部位の圧痛や血腫、皮内出血班(青あざ)咀嚼力(噛む力)の一時的な低下や開口障害(お口の開けにくさ)、噛みにくさ、咀嚼後のあごの疲れなどがあります。これらの症状は処置後1ヵ月以内に消失する症状です。 この他の副作用として、笑った時や口角が上がった時のお顔の変化、表情の変化や、口渇(お口が乾きやすい)を感じる場合もあります。 症状に合っていない過剰な濃度を注射すると、日常生活に多大な支障を与えることになります。間違った注射は、咀嚼機能(かみ合わせ機能)の低下、嚥下(飲み込む機能)、発音にも影響します。 薬剤が周囲へ漏れてしまうことで表情の変化が生じることもあります。また周囲組織の唾液腺である耳下腺へ漏出すると口渇(お口の渇き)を引き起こします。これらの症状は、不適切な部位への注射や過度なマッサージ、不適切な薬剤濃度、筋肉以外への薬剤の浸潤、拡散がおもな原因です。 その他、咬筋の廃用萎縮(縮まりすぎ)によって頬骨が目立つ場合もあります。BTX注射によって起こるメリット、デメリットだけでなく、顔面のシルエットの変化や表情の変化も事前に把握しておくことが大切です。 |
|---|
| 併用療法、 関連領域 |
歯科補綴物(詰め物、かぶせ物、デンタルインプラント、部分入れ歯、全部入れ歯、すっぽんデンチャー)の破損予防、かみ合わせ、噛みしめによって、かぶせ物や詰め物の脱落、破損予防、入れ歯の安定を良くする(過重負担緩和療法)、インプラント即時加重治療における過重負担軽減療法(長持ちインプラント)、歯周病の治療期間中の動揺歯(揺れている歯)の過重負担軽減療法(歯の揺れを予防する)、咬筋、側頭筋、内側翼突筋への治療、歯列矯正治療の歯並びを早く動かす(短期矯正歯科治療)、エラボト、小顔、フェイスライン、ほうれい線改善(審美、美容、顔面治療) |
|---|
アゴのコリ(咬筋)に
必要な人体の解剖
顎コリの主な原因の筋肉は咬筋である。咬筋は骨格筋に分類され、咀嚼筋の中でも閉口筋であり、左右両側性に運動し、側頭筋や内側翼突筋と連動して動く。
咬筋は浅層と深層の2層に分かれ、筋膜によって隔たれている。浅層は頬骨弓前方2/3から始まり、後下方に向かい下顎骨下方咬筋粗面と、内側翼突筋とスリングを作り停止する(斜めに走る)。
深層は頬骨弓後方2/3から始まり、縦下方に向かい下顎骨外面咬筋粗面に付着し、一部は内側翼突筋とスリングを形成する(垂直に走る)。
支配神経は三叉神経第三枝、咬筋神経である。
アゴのコリ(咬筋)治療の流れ

1. デザインと刺入点を把握
原因となっている咬筋筋肉の図示をおこない、注射液が目的の筋肉以外に漏れないように確認をします。
描いた図示のもとに、針を刺す位置を決めます。最も痛くなく、最も効果的な注射位置を決めます。
2. 注射部位のマーキング
注射に際して安全な領域を図示します。
1. 口角と耳珠の下縁を結びます(耳下腺導管の回避)
耳下腺は「おたふくかぜ」の時に腫れる唾液腺です。唾液を作る機能があります。ここに注射液が漏れると、口が乾く、ドライマウスの副作用が出ます。
2. 下顎角からオトガイ結節まで下顎骨下縁のラインを結びます(咬筋停止部)
エラの部分から顎先まで咬筋の付着、内側翼突筋とのスリング部分です。目的の部分以外に注射液が漏れるとタルミやしわの原因になります。
3. 下顎頭(関節頭)から下顎角まで垂線を引きます(下顎枝後縁)
この部分が筋肉の後方の境目になります。この部分より後ろへの注射や注射液が漏れると、口渇、肩こり、首のしわの原因になります。
4. 咬筋の前縁をマーキングします
マーキングをする際に患者様には奥歯で咬みしめて頂きます。咬筋の前縁をマーキングしたら、注射に必要な前方限界線がわかります。
この段階で、触診によって筋筋膜機能障害症候群(MPD)の有無を判定します。また、筋組織のスパスム、筋膜のスパスムの有無を判断し、コリの位置を特定します。
5. 咬筋の後縁をマーキングします(下顎枝後縁)
咬筋の後縁をマーキングする際も患者様に奥歯で強く咬みしめて頂きます。咬筋の後縁をマーキングすることで、注射に必要な咬筋の後方限界線を把握することができます。
この段階で、前縁と同様に触診によって筋筋膜機能障害症候群の有無を判定します。また、筋組織のスパスム、筋膜のスパスムの有無を判断し、コリの位置を特定します。
四角に囲まれた線の中が咬筋の筋腹の安全域といえます。
患者様の症状と注射する部位、咬筋の位置を再度確認し、もっとも咬筋のMPDやスパスムが触知できる位置を特定し、副作用の発現の抑制や効果的な注射に努めています。
3. 冷罨法と表面麻酔
注射の前に刺入、注入時の痛みの軽減のために、注射する部に表面麻酔をおこないます。表面麻酔はクリームのタイプの軟膏とシールのタイプのテープを貼ります。ダブルの表面麻酔で針を刺す時の痛みはありません。さらに、注射する部分をアイスパックで冷やします。冷やすことで内出血の予防に役立ちます。
4. 消毒
注射する部分の術野の消毒を行います。薬剤の効果を最大限に発揮するためにアルコールを含有していない消毒薬を使用します。
※消毒薬にアレルギーがある患者様は事前にお申し出ください。
5. 刺入、注入、注入深度について
切れが良く、痛みが少なくなりますから、針のカット面は上向きにします。マーキングした5ヵ所に各0.2mL(5単位)ずつ合計1mLの25単位を注射をおこないます。(症状や筋肉の状態などにより使用する薬の量や濃度は適宜増減しています。)
使用する針は30G、13㎜の長さを使用しています。刺入する角度は皮膚に対して90°です。
患者様には、奥歯で咬みしめてもらった状態で、注射をします。注射する際はマーキングした部位の咬筋をしっかりと把持します。
刺入深度は患者様によって個体差があります。また、深度の基準は使用する針によっても異なりますが、13㎜の針を使用する場合は、咬筋の浅層と深層に到達することが出来ます。咬筋は、筋膜という膜によって隔たれていて、深層、浅層の2つの層に分かれています。
BTXが、両方の層に均一に奏功するように、それぞれの層に打ち分けて注入しています。針をいちばん深く差した部位(深層)と針を6㎜ほど抜いた部位(浅層)で注入して、均一的な注射に努めています。
6. 冷罨法
注射治療後は患部を冷やすことで、内出血の予防や、痛みの予防に効果があります。
咬筋注射に際して
注意する解剖組織
■ 顔面神経下顎縁枝
■ 顔面動静脈
■ 耳下腺導管
■ 耳下腺
アゴのコリ(咬筋)に
関するコラム
BTX製剤使用による骨格筋と皮筋に対する顔面の治療効果の違いについて
BTXの治療効果は経時的に4期に分かれている。注射治療後の第一期は筋緊張減少期、第二期は筋容量減少期、第三期は筋緊張増加期、第四期は筋容量増大期である。
第一期である筋緊張減少期はBTX注射後、3~5日後から始まるとされている。処置後1週間を経過すると、咬みしめたときの咬筋や側頭筋の力瘤は術前と比較しても軟らかくなり、整容的にも筋線維の減少が確認できる。効果は12週ほど続く。第四期である筋容量の増大期は16週以降である。文献的には、6ヵ月後に筋の緊張は、ほぼ元に戻っているとされているが、筋容量は治療前より減少しており、1年以上減少するという報告もある。
表情筋などの皮筋への治療効果と、咬筋や側頭筋など骨格筋等への治療効果としての持続時間や効果判定は異なる。 顔コリである表情筋領域のBTXを使用する場面は筋の過緊張が出現している時期である。注射治療により、すぐに第一期である筋緊張減少期に入る。その後、患者様は治療効果が薄れてきたと実感するのは、第三期である筋緊張増加期である。
アゴのコリ(咬筋)と
小顔治療の違いについて
クレンチング、ブラキシズムの対症療法として咬筋や側頭筋へ使用した場合の治療効果が薄れるのは、患者様が無自覚の間の第三期である筋緊張増加期に筋緊張が出現している。つまりこの時期にはすでにクレンチングやブラキシズムが再燃している。
一方、小顔希望の患者様の場合にはお顔の見た目は、皮筋の領域にみられるような第三期の筋緊張増加期になっても「小顔」としての治療効果は減少しない。そして、第四期の筋容量増大期に入ってから、整容的な効果が減少しはじめ、治療効果の低下を実感することになる。
また、クレンチングやブラキシズムに対しての治療効果は、術者が口腔内の診察により、歯の咬耗状態や補綴物の状態、咬筋や側頭筋の触診による、筋スパスムの触知により治療効果の低下時期を判断することになる。
このように表情筋領域に比べると治療効果は長く続く傾向にあるが、永続的な治療ではないために、患者様の希望や状態に応じた再治療が必要といえる。クレンチングやブラキシズムの予防による歯の保護、かぶせ物の保護、インプラント保護のためには症状の再燃が生じてからではなく、第二期から第三期の間に再治療をおこなうことが推奨されている。